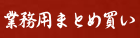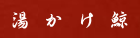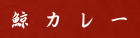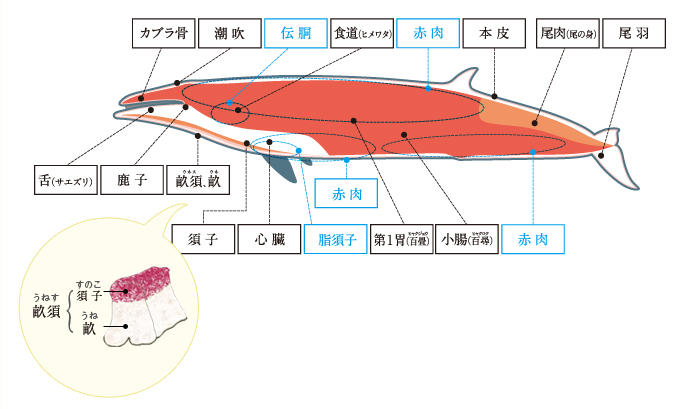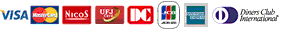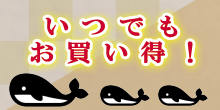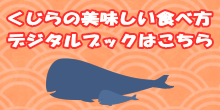日本の商業捕鯨再開について
日本の商業捕鯨再開と持続可能な水産資源の確保について
<商業捕鯨モラトリアムについて> (※1/IWC=国際捕鯨委員会 ※2/モラトリアム=一時停止)
1982年にIWC(※1)は、いわゆる商業捕鯨モラトリアム(※2)を採択しました。同時に遅くとも、1990年までに鯨資源を包括的に評価し、モラトリアムを見直すことが、付帯条件として決定されました。これに伴い日本は1987年漁期を最後に大型鯨類に対する商業捕鯨が一時的に停止されることとなりました。包括的評価により、IWCは少なくとも南極海ミンククジラは76万頭以上、オホーツク海・北西太平洋系のミンククジラは2万5千頭以上存在することを合意する一方で、改訂管理方式(RverceManegimentProsedure:RMP)を開発し、1994年のIWC総会においてRMPを鯨類資源管理措置とすることに合意しました。しかしながら、その後、保護のみを重視し、持続的利用を認めようとしない国々からの歩み寄りは見られず、モラトリアムの撤廃は実現しませんでした。2018年のIWC総会において鯨及び捕鯨に対する異なる意見や余地が無いことが明確になったことから、日本は2019年に6月30日を以てIWCより脱退しました。
<再開後の捕鯨状況>
日本は2019年7月1日より北西太平洋で3種(ニタリクジラ、イワシクジラ、ミンククジラ)に対する商業捕鯨を再開しました。再開に当たってはIWCが開発し、100年捕獲を継続しても資源に悪影響を与えないと認めた極めて保守的なRMPに沿って、多数のシミュレーションを通じて算出した捕獲可能量に基づき、捕鯨を行っています。
-----------------------------------------------------